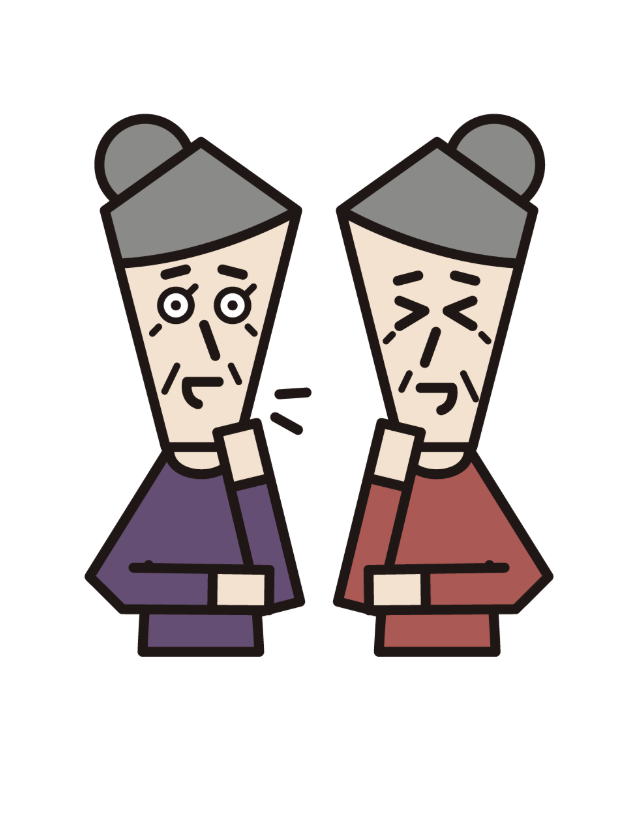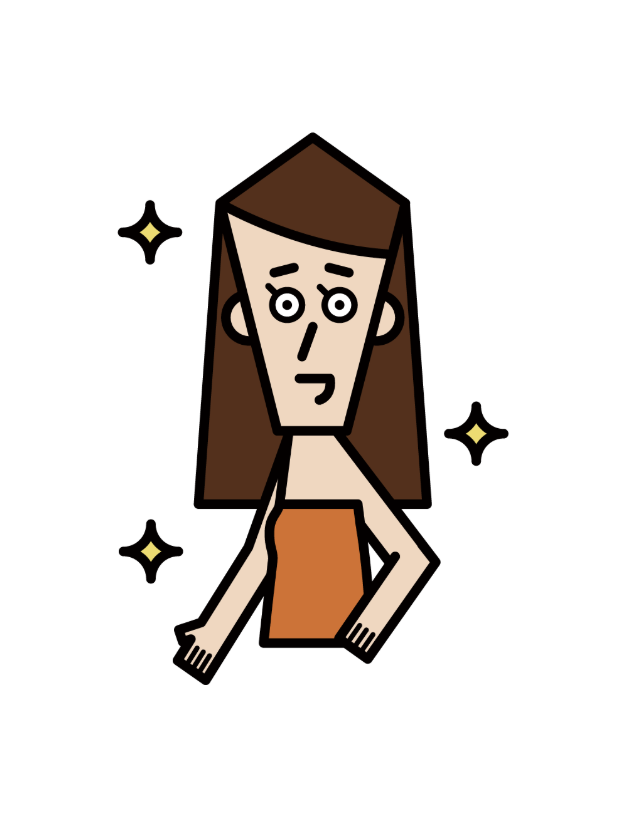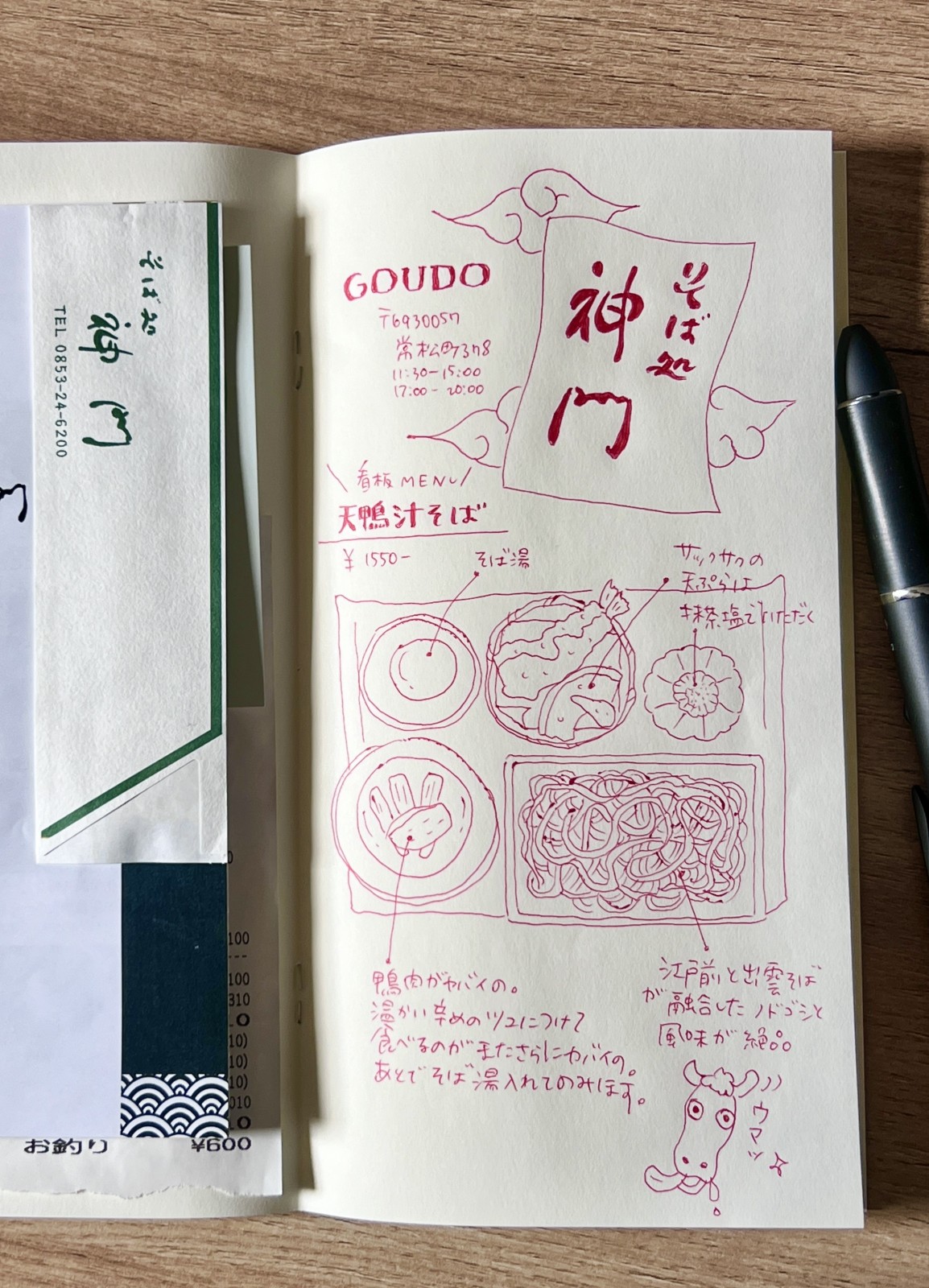神さまの甘味
出雲の山あいにある「もんぜん」。
一畑薬師へと続く参道沿い、右手にお店の姿が見えてくる。
ここに来た目的は、蕎麦といいたいところだが、今回は「ぜんざい」。
温かく、小豆の香りがふわりと広がり、心までほっとする。
やさしい甘さが口の中に広がる瞬間、思わず顔がにやけてしまう。
ところで、「ぜんざい」という言葉の由来をご存知だろうか。
かつて出雲では、「神在(じんざい)」の季節、神さまたちが集う際に温かい小豆を煮て供え、人々もそれをいただいたという。
この“じんざい”がやがて“ぜんざい”となり、全国に広まったのだとか。
つまり、ぜんざいは神さまたちの甘味、とも言えるのだ。
そして、奥さまがおすすめしてくれたそばガレットも絶品。
実は裏メニューのような存在らしい。
焼き立ての生地から立ち上る香ばしさ、ひと口ごとに素材の個性がくっきりと感じられ、それが見事に調和している。
思わず「こんな組み合わせが?」と驚くトッピングではあるが、それはぜひ実際に味わってのお楽しみ。
フランス料理の形式ながら、味の根底には確かに出雲の土地の風味が息づいている。
看板犬のテツくんもまた、癒しの存在。
窓の外には美しい景色、店内では実家にいるかのようにくつろげ、こってこての雲州平田弁で話す奥さまとの会話も楽しい。
すべてをひっくるめて、ぜひ一度訪れてほしいおすすめのお店だ。
出雲市小境町2117-3